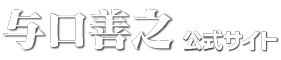「14万筆の重みを考えて」を考える
4月28日付 新潟日報 時事コラムに「14万筆の重みを考えて~県民投票条例案否決~」と題した記事がありました。一部引用しますが、『東京電力柏崎刈羽原発の再稼働の是非を問う県民投票条例案が県議会で否決された。議論を聞いていて、住民投票を巡る構図は四半世紀たっても変わっていないと感じた。特に県議の発言だ。県民は原子力工学やエネルギー政策などを理解するための十分な情報にアクセスできない場合が多い、などとする知事に対する質問があった。その結果、投票行動が一部の誤った情報に基づいて行われる恐れがあるとも指摘した。原発から遠くに住む人が自分ごととして投票できるのかとの疑問も投げかけた。もっと県民を信頼すべきではないだろうか。県民が情報にアクセスできないというのなら、分かりやすく判断材料を提供するのは地域代表である議員の役割だと思う。それが県民に対する責務ではないか。』というコラム記事です。
私も住民投票制度を調査・検討する過程で一般の住民に対する情報の重要性について自分なりに勉強しましたが、『行政は立地する地元に対しては大変熱心に通ったり、関係の方は非常な努力をされたわけであるが、一般の住民に対しては今までは十分な情報の提供とか説明が余りなされていなかった』との専門家の指摘もありました。一方、『住民に提供される情報の質・量が賛成論・反対論ともに公平かつ公正にされるのか?判断するに十分に正確な情報が提供されるのか?』という疑問を呈するものもありました。
原発の場合、安全性の説明は科学的であったり、専門的であったりすることから、一般住民が正確に理解することが出来るのか?読むことさえ拒まれるのではないか?とも考えられます。反対に、安全性に疑義を唱える場合は、過去の事故例を例示したり、万が一の場合どうするのかと疑問を呈したり、単に危ない、怖いということを言うことで、聞いた方は納得できてしまうのではないだでしょうか。また、その『万が一の場合』とは、どんな程度のどのような事象によって起こるのかなどの科学的な説明は十分示されているのだろうか。そして、情報が提供されたとしてもその情報の理解度が正しく一様になるとは考えられません。
『馬を水辺につれていけても水を飲ませることはできない』とは、本人にその気がないのに、周囲の人間が気を揉んだり強制しても無駄であるという例えですが、その例えが当てはまる場合も多いのではないでしょうか。情報をしっかり提供したとしても、その情報を受け取る方がそれぞれの考え方から、或いは、何も深く考えずにその情報を手に取らない場合も多々あるのではないでしょうか。その割合がどの程度ならば許容されるのか、又、その結果導かれる結果が信頼に足るものと言えるのか、私にはその判断基準が分かりません。
「県民が情報にアクセスできないというのなら、分かりやすく判断材料を提供するのは地域代表である議員の役割だと思う。」とも指摘されています。2013年6月に日本新聞協会が「新聞の公共性と役割~私たちはこう考えます~」というものを発表していますので、一部抜粋して記したいと思います。
『情報は日々の生活において、ものを考え、発言し、行動する上で重要な判断材料となります。新聞は政治、経済、社会、文化などあらゆる分野で記者が取材を通じて得た情報を分析、整理し、多様な論評などを加えながら一つのパッケージにして安定的に読者に提供しています。その点で新聞は自由な言論が保障されている民主主義社会においての必需品であり、極めて高い公共性を有しています。』という書き出しで始まり、『国や特定の企業、団体の支配や影響を受けることなく、国民の「知る権利」の奉仕者としての役割を果たすためには、憲法が定めた枠組みに安住するのではなく意識してそれを守り、強化する取り組みが必要だったのです。』、『情報発信を公的機関の一方的判断に委ねるのではなく、「第三者」の視点でチェックする姿勢、報道倫理に基づく取材に裏付けられた確かな情報を国民に提供する重要性と必要性は、むしろ高まっています。』とし、『国民が知識や情報を得る手段は、幅広く確保する必要があります。そのための重要な手段である新聞を国民が等しく、安く手にすることのできる環境を維持する努力が、健全な民主主義と豊かな未来を築く土台となるはずです。』と結んでいます。
分かりやすく判断材料を提供するのは議員の役割でもあると思いますが、新聞の役割も大きなものがあるのではないでしょうか。批判的視点でモノを見ることも大切ではありますが、第三者的視点で重要な判断材料である情報をあまねく提供できるのは、むしろ新聞であり、役割と大きな責務を負っていると言えるのではないでしょうか。
「もっと県民を信頼すべきではないだろうか。」とも言われていますが、「もっと議会・議員を信頼すべきではないだろうか。」ということも言えるのではないでしょうか。議会は、少なくとも4年に一度は選挙区ごとにではありますが、県民に審判を仰ぐことになります。議会・議員はある意味、身分・職責を賭して原子力発電所問題に限らず、様々な課題について判断をしています。責任を負うこと(負わせること)の出来ない県民の判断はどのような基準で行われるのでしょうか。好き・嫌い、安心・不安、安全性、経済性、温暖化対策への影響など多岐に渡る判断材料・基準を基に考えなければならないのでしょうが、県民それぞれが自らの考えを地域代表である議員に伝えることも大切なことではないでしょうか。県民投票条例の請求に際しては、様々な皆さんから要望を頂いきましたが、こうした議員への働きかけがもっとあっても良いのではないかと考えるところでもあります。